『コンテンツ文化史研究』第15号(2024年12月発行)

<投稿論文>
岡田正樹・柴台弘毅「ヴィジュアル系ミュージシャンは洋楽メディアとして機能したか? ―hideとSUGIZOの活動を事例に―」
永井健太郎「一九七〇年代のポップカルチャーにおける「公害」の表象―特撮ドラマ番組『スペクトルマン』の「公害怪獣」を事例に―」
<研究ノート>
若林晃央・伊藤千紗「日本のアニメにおける女子の色の変遷―一九六〇年代から二〇一〇年代までの通時的比較研究―」
<2022年度大会報告>
戸田千速「【開催報告】二〇二二年度大会シンポジウム「コンテンツとコミュニティ」」
<書評>
中山千里「大石学・時代考証学会(編)『明治・大正・昭和の時代劇メディアと時代考証』」
『コンテンツ文化史研究』第14号(2023年3月発行)

<投稿論文>
神谷和宏「アニメ・特撮のデフォルメキャラクターについての考察―その発生とゲームコンテンツによるアーカイブス性に着目して―」
齋藤雄一朗「日本における「近代的禁酒文化」形成過程の分析―酒造統制・社会衛生政策議論を中心に―」
劉茜「中国におけるキャラクターのコミュニケーション・ツール的受容―「羅小黒戦記」を例に―」
片山明久「現代観光の質的変化と「ものがたり創造」―京都府宇治市を事例に」
岡本健「コンテンツツーリズム史の構築―アニメ聖地作品の量的変化およびアニメ・マンガ・ゲームと観光・旅行とのかかわりの質的変化から」
<研究ノート>
森裕亮・田井浩人「アニメ聖地巡礼者の多様性と地域貢献の潜在性――サーベイの結果から」
高橋かおり「『アニメの社会学 —アニメファンとアニメ制作者たちの文化産業論』書評:社会学の観点から」
小林(七邊)信重「書評 浅野智彦『趣味縁からはじまる社会参加(若者の気分)』(岩波書店、2014年)」
『コンテンツ文化史研究』13号(2022年3月発行)
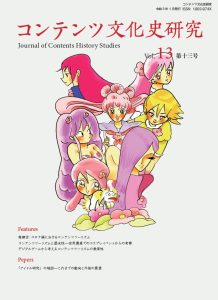
<特集 時間と空間からコンテンツツーリズムを考える>
岡本健「巻頭言:コロナ禍におけるコンテンツツーリズム」
菊地映輝「コンテンツツーリズムと歴史性 : 世界遺産でのコスプレイベントからの考察」
谷川嘉浩「デジタルゲームから考えるコンテンツツーリズムの教育性 : 記憶の参照、積層する記憶、確認とズレ」
<投稿論文>
田島悠来「「アイドル研究」の地図 : これまでの動向と今後の展望」
<研究ノート>
田川隆博「ローカルアイドルのアスピレーション : 東海地区のアイドルを事例として」
齋藤雄一朗「「禁酒文化」における「問題飲酒」概念の形成 : 「飲酒観」概念の視点から」
山田斗志希「台詞から見る悪役の造形 : テキストマイニングによる怪人二十面相と明智小五郎の台詞分析」
<在外研究レポート>
柳原伸洋「コンテンツの文化史とパブリックヒストリーの出会う場 : ザルツブルクの研究会「歴史で/歴史と遊ぶ」に参加して」
『コンテンツ文化史研究』12号(2021年1月発行)

<自由投稿論文>
高橋光輝・戸田千速「大学院におけるプロデューサー教育の研究 : 南カリフォルニア大学とデジタルハリウッド大学の比較の観点から」
湯天軼「「恋声」の研究 : 中国における日本声優とその声の受容をめぐる考察」
廣瀨涼「コンテンツの宗教性とマーケティング : 聖地巡礼におけるキャラクターの役割」
高艸賢「「アニソン」の経験と意味づけにおける文脈の複数性 : 水樹奈々ファンへのインタビュー調査から」
<研究ノート>
森田季節「ヴィジュアル系における「丘」の表現について」
<依頼論文>
柳原伸洋「モノから想起される二つのノスタルジー : ドイツのオスタルギーから日本の空襲マンガまで」
<書評>
佐藤寿昭「書評 赤川学『現代社会学ライブラリー9 社会問題の社会学』」
川﨑瑞穂「書評 中野敏男『詩歌と戦争 : 白秋と民衆、総力戦への「道」』」
<報告>
堀内淳一「コンテンツ文化史学会第十回大会「コンテンツ文化史研究の十年」報告」
『コンテンツ文化史研究』10・11号(2017年3月発行)

<自由投稿論文>
井手口彰典「コントローラブル・アイドル : 初音ミクにとっての二〇一〇年代」
高橋光輝・森利枝・戸田千速「コンテンツの学問化に関する考察」
山中智省「〈富士見文庫〉検証 : ライトノベルとジュブナイルポルノの”源流”をめぐって」
川﨑寧生「子供向けゲームコーナーの変遷」
三宅陽一郎「魔法少女のアニメーションの物語構造の進化 : ロボットアニメと比較した魔法少女アニメの物語構造分析」
河野至恩「コンテンツ文化の深化する受容・進化する翻訳 : 『All You Needs Is Kill』英訳・映画化の事例から」
須川まり「吉村公三郎が描く観光都市京都の境界線 : 『偽れる盛装』が見せる近代化する京都像」
『コンテンツ文化史研究』第9号(2015年8月発行)
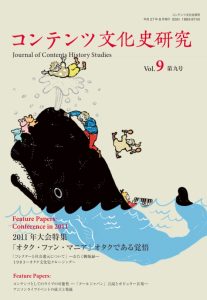
<特集:2011年大会「オタク・ファン・マニア:オタクである覚悟>
宇田川岳夫「「コレクターと社会還元について」―おたく懺悔録―」
永山薫「1983〜オタク文化史クルージング〜」
<特集:コンテンツとライブ>
宮入恭平「コンテンツとしてのライブの可能性―「クールジャパン」言説とポピュラー音楽―」
キムラケイサク「アニソンライブイベントの成立と発展」
<書評>
嵯峨景子「書評 久米依子『「少女小説」の生成 ジェンダー・ポリティクスの世紀』」
山中智省「書評 波戸岡景太『ラノベのなかの現代日本 ポップ/ぼっち/ノスタルジア』」
川﨑瑞穂「書評 安西信一『ももクロの美学 〈わけのわからなさ〉の秘密』」
『コンテンツ文化史学会2013年大会予稿集』(2013年12月刊行)
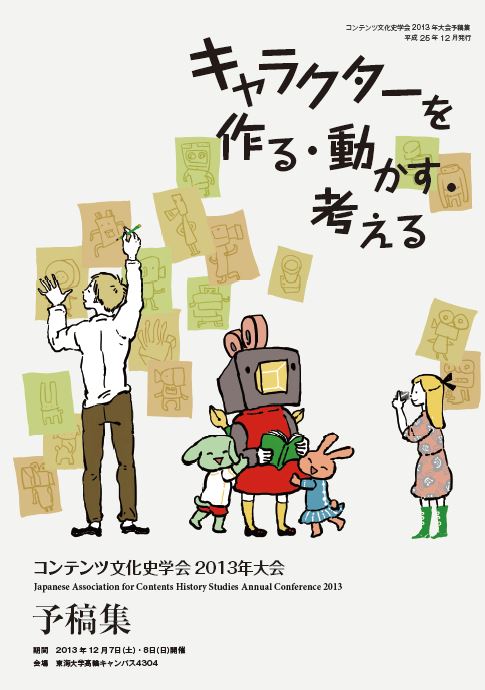
日高良祐「DTM文化の盛衰―1990年代のアマチュア・ミュージシャンによるMIDIデータ流通―」
高橋聡太「呼び屋と聴衆―戦後日本のポピュラー音楽産業における招聘コンサートの文化史―」
横えび「IPSはなぜ潰れないのか? ―石川をぷよぷよで染める会 17年のキセキ―」
石垣尚志「映画・映像コンテンツと地方都市の映画館」
七邊信重「「社会関係の拒絶」か「再帰的関係」か―コンテンツに見る「優しい関係」の出口―」
成田隆昭「韓国ロボットアニメに見る日本コンテンツからの影響について―70年代から80年代の韓国ロボットアニメを通して―」
原田伸一朗「キャラクターの「人権」―法学的人間の拡張と臨界―」
西貝 怜「宇宙・科学者・幸福―荒木哲郎監督アニメ『ギルティクラウン』における結晶と人の関係について―」
川﨑瑞穂「『サクラ大戦』のキャラクター設定にみる宝塚・松竹歌劇団の影響‐「歌劇団の系譜学」試論‐」
『コンテンツ文化史研究』8号(2013年7月刊行)
COMIC ZINでの取り扱いページはこちら。
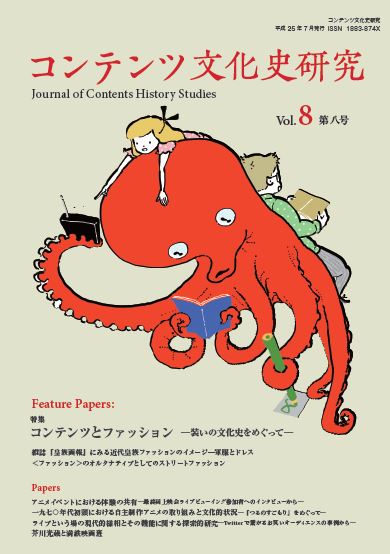
<自由投稿論文>
山口晶子「アニメイベントにおける体験の共有―最終回上映会ライブビューイング参加者へのインタビューから―」
玉井建也・吉田正高「一九七〇年代初頭における自主制作アニメの取り組みと文化的状況―『つるのすごもり』をめぐって―」
高橋みちな「ライブという場の現代的様相とその機能に関する探索的研究―Twitterで繋がるお笑いオーディエンスの事例から―」
クラマー羽奈江「芥川光蔵と満鉄映画班」
<特集:コンテンツとファッション-装いの文化史をめぐって->
青木淳子「雑誌『皇族画報』にみる近代皇族ファッションのイメージ―軍服とドレス」
渡辺明日香「<ファッション>のオルタナティブとしてのストリートファッション」
<書評>
牧 和生「書評 岡本健『n次創作観光 アニメ聖地巡礼/コンテンツツーリズム/観光社会学の可能性』」
川﨑瑞穂「書評 濱野智史『前田敦子はキリストを超えた――〈宗教〉としてのAKB48』」
『コンテンツ文化史学会2012年大会予稿集』(2012年12月刊行)
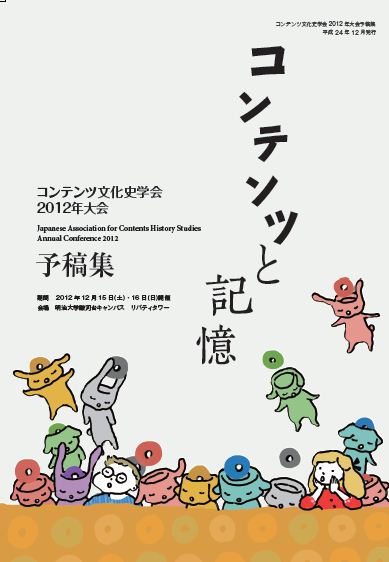
<自由論題発表>
川﨑瑞穂「ルネ・ジラールの理論からみるコンテンツ文化―アイドルグループSKE48の楽曲分析を中心に―」
<テーマ発表>
牧和生「コンテンツ文化と記憶―限定合理性の経済学の観点から―」
水上恵太「ファミコン時代の新規参入と開発」
永田大輔「メディア使用から立ち上がる我々意識―一九八〇年代におけるビデオとアニメ雑誌の再帰的関係から」
山中智省「あの日見た文庫の存在意義を僕達はまだ知らない―八〇年代OVAノベライズの動向と富士見美少女文庫―」
横えび・test_lockit「電脳連鎖がぷよらーを襲う―ぷよぷよAI 構築の記憶―」
冨澤美典「マンガにおける「コンテンツデータ」の保存と管理について」
〈特別講演〉
おにたま「アーケードビデオゲーム文化の保存と研究」
『コンテンツ文化史研究』7号(2012年4月刊行)
COMIC ZINでの取り扱いページはこちら。DLsiteでの取り扱いページはこちら。

<インタビュー>
米光一成氏インタビュー コンテンツクリエイターの「生き方」をめぐって
<自由投稿論文:研究ノート >
下條正純「「マリア様がみてる」における女性文末辞と人物描写」
井手口彰典「コミケットの「ジャンルコード一覧」
<二〇一〇年大会特集>
二〇一〇年大会「大学におけるコンテンツ教育の現状と課題」
<特集「少女」の歴史、ときめきの軌跡>
嵯峨景子「明治末期の少女雑誌にみる投稿作文と文体形成—
塚口綾子「少女が愉しむ恋愛ゲーム」
沼田知加「マンガが拓く「女子」の未来—描く女たちは、
<参加記>
ルジラット・ヴィニットポン「
『コンテンツ文化史研究』6号(2011年10月刊行)
COMIC ZINでの取り扱いページはこちら。DLsiteでの居り扱いページはこちら。
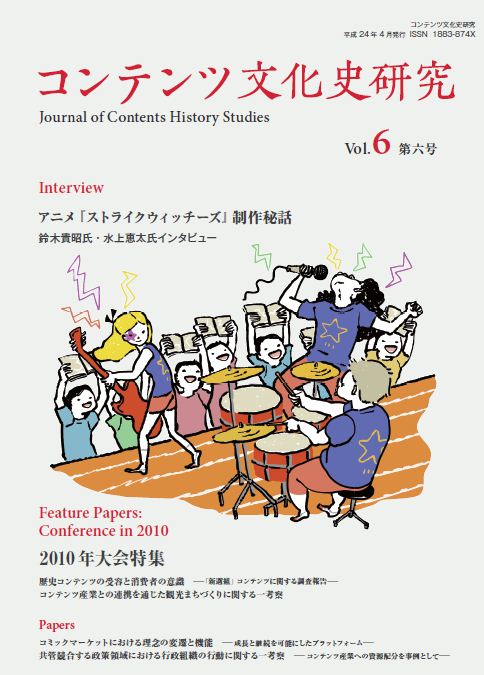
<インタビュー>
鈴木貴昭氏・水上恵太氏インタビュー アニメ『ストライクウィッチーズ』制作秘話
<自由投稿論文 >
岡安英俊・三崎尚人「コミックマーケットにおける理念の変遷と機能――成長と継続を可能にしたプラットフォーム」
中村仁「共管競合する政策領域における行政組織の行動に関する一考察―コンテンツ産業への資源配分を事例として―」
<二〇一〇年大会特集>
堀内淳一「歴史コンテンツの受容と消費者の意識 ―「新選組」コンテンツに関する調査報告―」
戸田千速「コンテンツ産業との連携を通じた観光まちづくりに関する一考察」
<書評>
戸田千速「高橋光輝著『コンテンツ教育の誕生と未来』」
鴫原盛之「加藤裕康著『ゲームセンター文化論―メディア社会のコミュニケーション―』」
『コンテンツ文化史学会2011年大会予稿集』(2011年12月刊行)
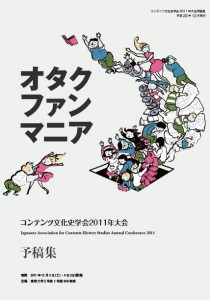
玉井建也・吉田正高「1970年代初頭の自主制作アニメの取り組みと文化的状況―『つるのすごもり』に着目して―」
花岡敬太郎「戦後ヒーロー像の変遷に見る、日本人の「戦争」への問題意識―『ウルトラマン』『仮面ライダー』を中心に―」
池田拓生「観光者創造観光における観光者の主体性」
牧和生「オタク文化における共感という解釈について」
永田大輔「「第三のメディア」としてのOVAとオタク―八十年代のアニメ雑誌から」
中川譲「「オタク」の用いられ方についての量的調査―新聞記事を題材に「オタク」の大衆化を考える―」
三宅陽一郎「日本のアニメーションにおける人工知能の描かれ方」
『コンテンツ文化史研究』5号(2011年4月刊行)
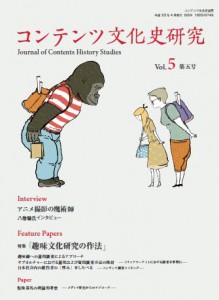
Comic ZINの取り扱いページはこちら。DLsiteでの取り扱いページはこちら。
<インタビュー>
八巻磐氏インタビュー-アニメ撮影の魔術師-
<2009年大会の記録>
「アマチュア文化とコンテンツの未来」パネルディスカッションの記録
<自由投稿論文>
平井智尚「聖地巡礼の理論的考察—メディア研究からのアプローチ—」
〈特集「趣味文化研究の作法」〉
特集「趣味文化研究の作法」にあたって
〈依頼論文〉
浅野智彦「趣味縁への量的調査によるアプローチ」
玉川博章「サブカルチャーにおける量的および質的調査方法の検討—コミックマーケットにおける調査を事例に—」
小山友介「日本社会内の創作者の「厚み」をしらべる—コンテンツ調査メイキング—」
<書評>
樺島榮一郎「デジタルゲームの教科書制作委員会著『デジタルゲームの教科書知っておくべきゲーム業界最新トレンド』」
山﨑鎮親「古賀令子著『「かわいい」の帝国—モードとメディアと女の子たち』」
<参加記>
横えび「コンテンツ文化史学会第2回例会「ゲーム産業は、いかにして成立しえたのか——アメリカ、日本…草創期に何が生じたのか」」
二〇一〇年度コンテンツ文化史学会総会の記録
『コンテンツ文化史学会2010年大会予稿集』(2010年11月刊行)
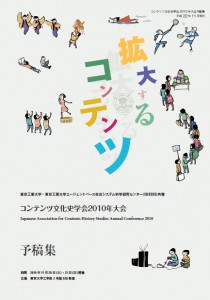
<自由論題発表>
玉井建也「明治期における本土から見た琉球認識―「豊臣秀頼琉球征伐」をめぐって」
中村晋吾「様々なる衣裳、可視化される世界―宮澤賢治「ビヂテリアン大祭」をカーライル「衣裳哲学」から読み解く」
大島十二愛「新聞記者時代の久留島武彦と子ども向けジャーナル―中央新聞『ホーム』のデジタル化保存と分析を中心に―」
<テーマ発表>
小山友介「JRPGの誕生と概念の吟味」
山根信二「ゲームの研究と教育における大学の戦略」
戸田千速「コンテンツ産業化が進む鉄道産業に関する一考察」
堀内淳一「歴史コンテンツの受容に関する実態調査―「新撰組」コンテンツに関する調査報告」
『コンテンツ文化史研究』4号(2010年10月刊行)
COMIC ZIN取り扱いページはこちら。DLsiteでの取り扱いページはこちら。
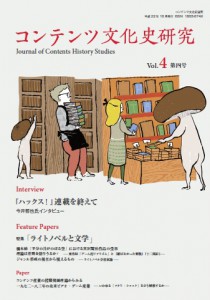
<インタビュー>
今井哲也氏インタビュー ―『ハックス!』連載を終えて―
<自由投稿論文>
樺島榮一郎「コンテンツ産業の段階発展理論からみる一九七二~八三年の北米ビデオ・ゲーム産業―いわゆる「アタリ・ショック」をどう解釈するか―」
〈特集「ライトノベルと文学」〉
特集「ライトノベルと文学」にあたって
〈依頼論文〉
大島丈志「橋本紡「半分の月がのぼる空」における宮沢賢治作品の受容」
井上乃武「理論は差異を語りうるか?――東浩紀「ゲーム的リアリズム」と『選ばなかった冒険』『十二国記』」
山中智省「ジャンル形成の現在から視えるもの ―ライトノベル分析試論―」
<書評>
岡本健「増淵敏之著『物語を旅するひとびと コンテンツ・ツーリズムとは何か』」
<第一回例会の記録>
『コンテンツ文化史研究』3号(2010年4月刊行)
COMIC ZINの取り扱いページはこちら。DLsiteの取り扱いページはこちら。
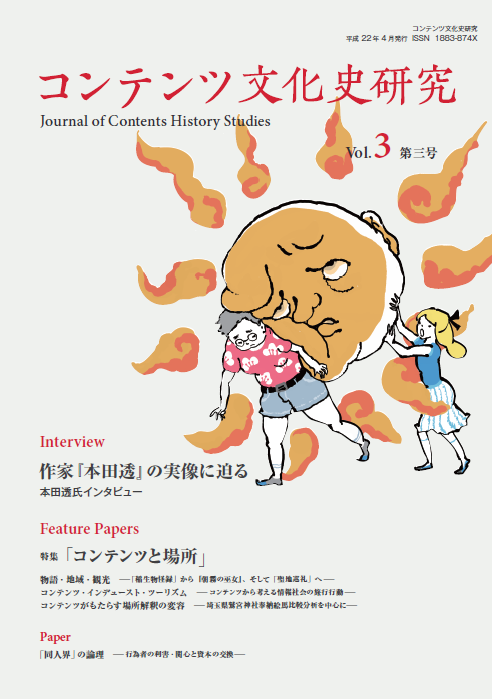
<インタビュー>
本田透氏インタビュー
<自由投稿論文>
七邊信重「「同人界」の論理―行為者の利害-関心と資本の変換―」
〈特集「コンテンツと場所」〉
特集「コンテンツと場所」にあたって
〈依頼論文〉
玉井建也「物語・地域・観光―「稲生物怪録」から『朝霧の巫女』、そして「聖地巡礼」へ―」
〈投稿論文〉
岡本健「コンテンツ・インデュースト・ツーリズム―コンテンツから考える情報社会の旅行行動―」
今井信治「コンテンツがもたらす場所解釈の変容―埼玉県鷲宮神社奉納絵馬比較分析を中心に―」
<参加記>
三宅陽一郎「IGDA日本代替現実ゲーム部会 第一回研究会「ARG入門:体験型エンタテインメントの現在と未来」参加記―新しいコンテン ツの展開の形 ARG (Alternate Reality Game) ―」
<書評>
山口浩「出口弘・田中秀幸・小山友介編『コンテンツ産業論―混淆と伝播の日本型モデル―』」
<第二回例会の記録>
<二〇〇九年度コンテンツ文化史学会総会の記録>
『コンテンツ文化史研究』2号(2009年10月刊行)
COMIC ZINの取り扱いページはこちら。DLsiteの取り扱いページはこちら。
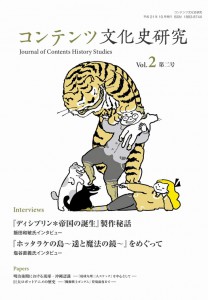
<インタビュー>
飯田和敏氏インタビュー 『ディシプリン*帝国の誕生』製作秘話
塩谷直義氏インタビュー 『ホッタラケの島~遥と魔法の鏡~』をめぐって
<論文>
安藤奈々・玉井建也「明治後期における琉球・沖縄認識―「琉球九州三人スケッチ」を中心として―」
富澤達三「巨大ロボットアニメの社会史―『機動戦士ガンダム』登場前夜まで―」
<参加記>
七邊信重「 IGDA日本同人・インディーゲーム部会第二回研究会「ゲームデザインとメイキング」参加記」
玉井建也「米沢嘉博記念図書館開館記念シンポジウム「マンガ・アニメ・ゲーム・フィギュアの博物館学」に参加して」
<書評>
樺島榮一郎「濱野智史『アーキテクチャの生態系』」
<第一回例会の記録>
<二〇〇九年度部会活動の記録>
『コンテンツ文化史研究』 創刊号(2009年4月刊行)
紙媒体は売り切れ。DLsiteにてDL販売中。

<ご挨拶>
吉田正高「コンテンツ文化史のあゆみ―学会誌の創刊ご挨拶にかえて―」
<論文>
中村晋吾「「オタク文化」時代に宮沢賢治を読む—「擬人化」の諸様態をめぐって」
玉井建也「「聖地」へと至る尾道というフィールド—歌枕から『かみちゅ!』へ—」
七邊信重「同人・インディーズゲーム制作を可能にする「構造」―制作・頒布の現状とその歴史に関する社会学的考察―」
井上明人「作品を解体し、融合させるシステム—ファイナルファンタジーシリーズを例に」
<書評>
鳴海拓志「長谷川文雄、福冨忠和編『コンテンツ学』」
玉井建也「奥野卓司『ジャパンクールと情報革命』」
<参加記>
玉井建也「東京大学大学院情報学環シンポジウム「コンテンツ教育の未来へ」に参加して」
