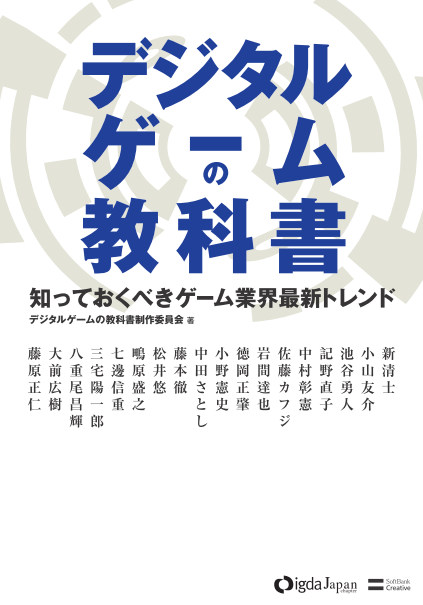下記の要領で2010年第1回例会「趣味文化研究の作法」を開催いたします。参加は事前登録制となっております。お手数ですが参加申込フォームより登録をお願いいたします。
—-
第1回例会「趣味文化研究の作法」
概要
コンテンツの消費や生産を含む、いわゆる「趣味文化」一般を、「私語り」や「主観的印象論」、あるいはデータなき「誇大理論」に陥らずに、いかに調査・研究していくかを考えることは、コンテンツ研究を学問として成立させる上でも重要な課題であろう。今回の例会では、同人誌製作者や鉄道ファンについて、質的・量的研究を行って来られた、3人の研究者の方に、これまでの研究成果についてご発表いただく。その上で、趣味文化についてどういった問いを立てられたか、研究対象をどういう理論的関心に基づいて構成したか、いかに回答者やインフォーマント(情報提供者)を探し出したか、先行研究をどのように集めたか、いかなる枠組みを用いて分析を行ったか、といった課題について、フロア全体で議論を行う。趣味文化の経験的研究にまつわる実践的・理論的問題について、さまざまな方々と情報交換ができれば幸いである。
参加申込フォーム
http://www.contentshistory.org/event_entry/
当日参加につきましては申込の状況に応じアナウンスさせていただきますので、こまめに学会ウェブサイトをご確認くださいますよう、お願い申し上げます。
日時:
6月26日(土)12時半開場、13時開始
場所:
キャンパスイノベーションセンター東京 2F多目的室2 (JR田町駅近く)
http://www.cictokyo.jp/index.html
参加費:
500円(会員は無料)
司会:
七邊信重(東京工業大学エージェントベース社会システム科学研究センター)
発表者:
浅野智彦 (東京学芸大学)「趣味縁への量的調査によるアプローチ」
玉川博章 (メディア開発綜研)「コミックマーケットにおける調査アプローチの課題」
小山友介 (芝浦工業大学)「日本社会内の創作者の「厚み」をしらべる」
タイムスケジュール
13:00-13:20 趣旨説明(七邊)
13:20-14:00 浅野智彦(東京学芸大学) 「趣味縁への量的調査によるアプローチ」
14:00-14:10 休憩
14:10-14:50 玉川博章(メディア開発綜研) 「コミックマーケットにおける調査アプローチの課題」
14:50-15:30 小山友介(芝浦工業大学) 「日本社会内の創作者の「厚み」をしらべる」
15:30-15:40 休憩
15:40-16:40 総合討論